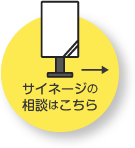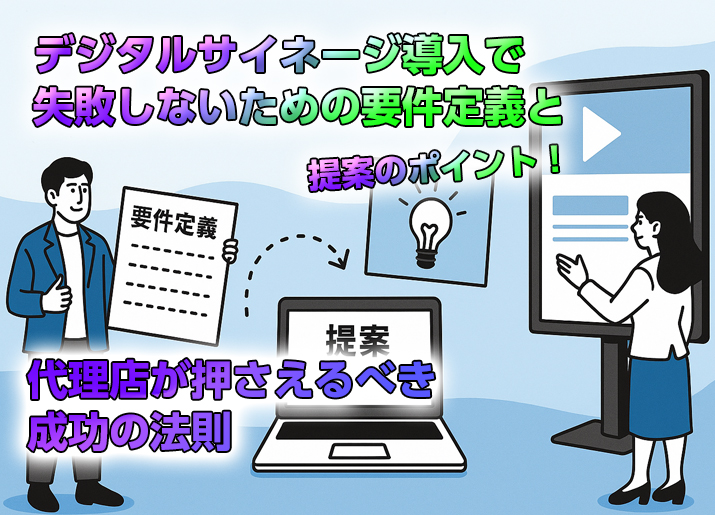By デジタルサイネージディレクター:t.takita Posted
駅でつい見てしまうサイネージとは?プロが教えるコンテンツ制作成功への4ステップ

駅のデジタルサイネージは、日々多くの人が行き交う交通インフラの中で、高い広告効果を発揮するメディアとして注目されています。しかし、いざ制作を始めようとすると「何から手をつけてよいか分からない」「効果的な映像の作り方が分からない」と悩む担当者も多くいます。
私もこれまで多くのサイネージコンテンツ制作を手がけてきた中で、成功には明確なプロセスと専門的なノウハウが不可欠だと感じています。特に駅という特殊な環境では、一般的な映像制作とは異なる技術が必要です。
本記事では、初めての方でも実践できるよう、駅デジタルサイネージの基礎から制作手順、実践的ノウハウまでを解説します。
目次
駅デジタルサイネージとは
駅デジタルサイネージとは、鉄道駅の構内に設置されたデジタルディスプレイを活用した広告・情報発信システムのことです。従来の紙製ポスターや看板に代わり、液晶ディスプレイやLEDパネルを使用してリアルタイムでコンテンツを配信できる次世代型の広告媒体として普及してきました。
この技術革新により、静止画だけでなく動画コンテンツの配信が可能になったことで、表現力の幅が大幅に広がりました。しかし、それと同時にコンテンツ制作の複雑さも増しており、効果的な映像を制作するためには専門的な知識と技術が必要になっています。
現在、首都圏を中心にJR東日本の「J・ADビジョン」、東京メトロの「メトロステーションビジョン」をはじめとして、各鉄道会社が独自のデジタルサイネージネットワークを展開しており、それぞれ異なる技術仕様やコンテンツ制作要件が設定されています*¹。
駅サイネージ導入のメリット・デメリット
駅デジタルサイネージの導入を検討する際、まずはそのメリットとデメリットを正確に把握することが重要です。
メリット
高い視認性と到達率が挙げられます。駅は多くの人が日常的に利用する場所であり、通勤・通学による反復接触効果も期待できます*¹。また、リアルタイムでのコンテンツ更新が可能で、時間帯や曜日に応じた最適な広告配信ができることも大きな利点です*²。
デメリット
初期導入費用が高額になる場合があり、継続的な運用コストも発生します。また、駅という公共空間では音声出力に制限があるため、視覚的な訴求力に依存することになります。さらに、競合他社の広告も多数存在するため、注意を引くためのクリエイティブな工夫が必要です。
デジタルサイネージの種類と特徴
駅で展開されるデジタルサイネージには、設置形態によっていくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解することで、目的に応じた最適なコンテンツ制作が可能になります。
縦型柱面サイネージ
駅構内の柱に設置される縦型サイネージは最も一般的なタイプです。55型~75型テレビサイズ(幅約1.2m、高さ約0.7m~1.7m)のディスプレイが使用され、9対16の縦長アスペクト比が特徴です*³。この縦長フォーマットを活かしたコンテンツ制作では、上下の視線移動を意識したレイアウト設計が重要になります。
複数面が連続して設置される場合、移動中の利用者に段階的に情報を伝える「シーケンシャル展開」という手法が効果的です。例えば、1画面目で注意を引き、2画面目で商品の魅力を伝え、3画面目で行動喚起を行うといった、映画的な演出手法を活用できるのが大きな魅力です。
大型LEDビジョン
改札口やコンコースに設置される大型LEDビジョンは、大型スクリーンサイズ(100型テレビ以上、幅約2.2m、高さ約1.2m超)を持ち、最も高い視認性とインパクトを提供します。4K対応が標準で、細部まで美しく表現できるため、ブランドイメージを重視したハイクオリティなコンテンツ制作に最適です*³。
このタイプのサイネージでは、大画面の迫力を最大限に活かしたダイナミックな映像表現が可能です。特に、商品の質感や細かなディテールを美しく見せることができるため、高級ブランドや精密機器などの訴求に威力を発揮します。制作時は、大画面での視聴を前提とした高解像度素材の準備と、インパクトのあるビジュアルデザインが成功の鍵となります。
ホームドアサイネージ
電車のホームドアに内蔵されたディスプレイは、独特の視聴環境を提供します。電車待ちの時間は平均3分から8分程度確保できますが、実際の広告への注目時間は限られており、効果的なコンテンツ設計が重要です*⁴。視認距離も1メートルから2メートルと近いため、詳細な情報提供に適しています。
この環境の特性を活かしたコンテンツ制作では、時間をかけてじっくりと商品やサービスの魅力を伝えることができます。ストーリーテリング手法を用いた感情に訴える映像や、商品の使用方法を丁寧に説明するハウツー動画などが特に効果的です。
インタラクティブサイネージ
タッチパネル機能を備えたインタラクティブサイネージは、利用者との双方向コミュニケーションを可能にします。駅構内の案内情報や、商品カタログ、多言語対応サービスなどで活用されています。
このタイプのコンテンツ制作では、ユーザーインターフェース(UI)設計が重要な要素となります。直感的に操作できるデザインと、タッチ操作に最適化されたコンテンツ構成が必要です。また、タッチ操作の反応速度や操作感にも配慮した制作が求められ、従来の映像制作とは異なる専門的なスキルが必要になります。
スマートサイネージ
IoT技術と連携したスマートサイネージは、環境データや利用者の行動データに基づいて、自動的にコンテンツを切り替える次世代型のシステムです。天候や時間帯、混雑状況などに応じて最適なコンテンツを配信できます。
このシステム向けのコンテンツ制作では、様々な状況に対応できる複数バリエーションの制作が必要になります。例えば、雨の日用、晴れの日用、朝用、夜用といった具合に、シーンごとに最適化されたコンテンツを用意する必要があり、制作計画と管理が重要な要素となります。
効果的な配置場所の選定方法
コンテンツ制作において、設置場所の特性を理解することは制作方針を決定する重要な要素です。
ターゲット属性による駅選定
ビジネス層を狙う場合、新橋駅や品川駅が効果的です。30代から50代のサラリーマンやOLが多く利用するため、落ち着いたトーンの映像表現や、信頼性を重視したコンテンツ設計が適しています*⁵。コンテンツ制作では、ビジネスシーンでの活用をイメージさせる映像や、効率性や機能性を前面に押し出した訴求が効果的です。
若年層をターゲットとする場合は渋谷駅が最適です。ファッションやエンタメに敏感な10代から20代が多く、SNSとの親和性も高いため、トレンド感のある映像表現や、若々しく活気のあるコンテンツが求められます。制作時は、最新の映像トレンドやSNSで話題になりやすいビジュアル表現を取り入れることが重要です。
動線分析による設置位置
改札口正面はすべての利用者が通過する場所で最も確実に情報を届けられますが、短時間で理解できるシンプルなメッセージが求められます。この場所向けのコンテンツは、3秒以内に核心を伝える「瞬間訴求型」の制作手法が必要で、強いビジュアルインパクトと明確なメッセージが成功の鍵となります*⁶。
エスカレーター前は利用者が立ち止まる場所で、比較的長い時間をかけて情報を伝えることができます。この環境では、15秒から30秒程度の「ショートストーリー型」コンテンツが効果的で、商品の魅力を段階的に伝える映像構成が可能です。
コンテンツ制作手順
効果的なサイネージコンテンツの制作には、体系的なアプローチが必要です。以下の4つのステップで進めることで、プロフェッショナルな品質のコンテンツを効率的に制作できます。
●デジタルサイネージコンテンツの種類とその重要性はこちら
ステップ1:企画・戦略策定とコンセプト設計
コンテンツ制作の成功は、明確な企画・戦略策定から始まります。まず、制作目的を具体的に設定します。認知度向上、売上増加、ブランディング強化など、目的によって映像の表現手法や構成が大きく変わるためです。
次に、ターゲットペルソナを詳細に設定します。駅利用者の年齢層、職業、ライフスタイル、駅利用目的を分析し、そのペルソナが好む映像表現やメッセージトーンを検討します。例えば、朝の通勤時間帯のビジネスパーソンであれば、効率性や実用性を重視した映像表現が適しています。
コンセプト設計では、駅という特殊な環境を考慮した「3秒ルール」を意識し、瞬間的に注意を引くビジュアルフックと、短時間で理解できるシンプルなメッセージ構造を設計します。この段階で、映像の全体的なトーンやスタイル、色彩設計の方向性も決定します。
ステップ2:詳細コンテンツ設計と絵コンテ制作
企画が固まったら、具体的な映像設計に入ります。まず、サイネージの画面仕様(サイズ、アスペクト比、解像度)に応じた最適なレイアウトを設計します。縦型画面では縦の視線移動を活かしたレイアウト、横型画面では左右の情報配置バランスが重要です。
絵コンテ制作は、コンテンツ制作において最も重要なプロセスの一つです。1秒単位でのシーン構成を決定し、カメラワーク、文字情報の表示タイミング、音声(使用可能な場合)のタイミングを詳細に設計します。駅サイネージでは特に、移動中の視聴者を考慮した「視線誘導設計」が重要で、どこに注目してもらいたいかを明確に設定します。
情報の優先順位付けも重要です。限られた時間内で伝えるべき情報を整理し、最重要情報(ブランド名、商品名)、重要情報(キャッチコピー、価格)、補助情報(詳細説明、連絡先)の階層構造を明確にします。
ステップ3:プロフェッショナル映像制作
実際の映像制作では、駅の特殊な視聴環境を考慮した高品質な制作が必要です。まず、素材準備では4K解像度以上の高画質素材を用意し、大型ディスプレイでも美しく表示できるよう配慮します。
色彩設計では、駅の照明環境(主に蛍光灯)下での見え方を考慮し、やや暖色系に調整することが多いです。また、背景との十分なコントラストを確保し、文字情報の可読性を最優先に設計します。
動画制作では、15秒から30秒程度の短時間で最大限の効果を発揮する「コンパクト設計」が重要です。音声制限を前提とした視覚的な表現に特化し、動きやアニメーションで注意を引きつつ、テキスト情報で具体的な内容を伝える構成にします*¹。
テキスト設計では、視認距離3~10メートルを想定したフォントサイズの選択が重要です。ゴシック体などの可読性の高いフォントを使用し、1画面あたり30文字以内に抑えることで、移動中でも読みやすくします*⁶。
●デジタルサイネージ動画の目的と種類はこちら
ステップ4:品質管理と専門的サポート
制作完了後の品質管理は、プロフェッショナルなコンテンツの必須要素です。実際のディスプレイ環境での表示テストを行い、色再現性、文字の可読性、動画の滑らかさを確認します。
特に重要なのは、異なる時間帯の照明環境での見え方の確認です。朝の自然光が入る時間帯と、夜の人工照明下では、同じコンテンツでも見え方が大きく変わるためです。
品質確認項目として、技術面では解像度、ファイルサイズ、フォーマット適合性を、内容面では誤字脱字、ブランドガイドライン適合性、法的コンプライアンスを厳密にチェックします。
高品質な駅サイネージ制作には専門知識と経験が不可欠
上記の専門的な制作プロセスを社内だけで完璧に実行するには、相当な経験と専門知識が必要です。特に駅という特殊な環境に最適化されたコンテンツ制作は、実際の運用経験から培われるノウハウが重要な要素となります。初回制作や、より高品質なコンテンツを求める場合は、豊富な制作実績を持つ専門会社に相談することで、効率的かつ確実な成果を期待できます。
●デジタルサイネージコンテンツの制作依頼方法はこちら
駅別コンテンツ戦略
駅によって利用者属性が異なるため、それぞれに適したコンテンツ制作戦略が必要です。
主要ターミナル駅向けコンテンツ
新宿駅は多様な属性の利用者がいるため、汎用性の高いコンテンツ設計が効果的です。制作時は、幅広い年齢層に訴求できるユニバーサルなビジュアル表現と、誰にでも理解しやすいシンプルなメッセージ構成を心がけます。時間帯別に異なるバージョンを制作し、朝はビジネス向け、昼は主婦・シニア向け、夜はエンタメ向けといった使い分けも効果的です。
渋谷駅では若年層に響くトレンド感のある映像表現が重要です。最新の映像技術やSNSで話題になりやすいビジュアルスタイルを取り入れ、SNS投稿を促すような話題性のあるコンテンツ設計を行います。カラフルで動きのある表現や、インフルエンサーを起用した親近感のある演出が効果的です。
東京駅では高所得層向けの上質なコンテンツが求められます。洗練されたビジュアルデザインと高級感のある映像表現、品質の高さを感じさせる細やかな演出が重要です。制作時は、素材の質感や色調に特にこだわり、プレミアム感を演出します。
時間帯別コンテンツ制作
朝の通勤ラッシュ時向けコンテンツは、時間に追われる利用者に配慮したスピーディーな構成が必要です。3秒以内に核心を伝える「瞬間理解型」の制作手法を用い、強いビジュアルインパクトと簡潔なメッセージで構成します。朝食、コーヒー、ビジネスツールなど、朝の生活に密着した商品・サービスの訴求が効果的です。
昼間時間帯は比較的ゆったりとした視聴が可能なため、詳細な情報を含む「情報提供型」コンテンツが適しています。商品の特徴や使用方法を丁寧に説明し、QRコードを活用した詳細情報への誘導も効果的です。主婦層向けの生活用品や、シニア層向けの健康関連商品などの訴求に向いています。
プロフェッショナルコンテンツ制作のポイント
駅デジタルサイネージで成果を上げるためには、一般的な映像制作とは異なる専門的な制作技術が必要です。
駅環境に特化した制作技術
音声制限環境での映像制作では、視覚的な情報伝達力を最大化する必要があります。効果的な手法として、文字アニメーションを活用した動的なテキスト表現や、商品の動きや使用感を視覚的に表現するモーショングラフィックスの活用があります。
また、移動中の視聴者を考慮した「モーション・ストップ理論」の適用も重要です。画面内の動きを計算し、歩行中でも内容を認識できるような動きの速度と方向を設計します。
制作効率を上げる実践的手法
効率的なコンテンツ制作のためには、テンプレート化とモジュール化が有効です。基本的なレイアウトパターンをテンプレート化し、商品やサービスに応じてビジュアル要素を差し替えることで、制作時間の短縮と品質の安定化を図れます。
また、素材ライブラリーの構築により、頻繁に使用するアイコン、フォント、カラーパレット、アニメーションパターンを整理しておくことで、制作作業の効率化が可能です。
しかし、これらの専門的な制作技術を社内で一から習得するには相当な時間と労力が必要です。特に、駅サイネージ特有の制作ノウハウは実際の運用経験から培われるものが多く、初回制作では多くの試行錯誤が必要になるのが現実です。
運用・配信システムの選択
効果的なコンテンツ制作と並行して、適切な配信システムの選択も重要です。
クラウド型システムは初期導入コストが抑えられ、遠隔からのコンテンツ更新が可能です。制作したコンテンツをリアルタイムで配信でき、A/Bテストによる効果検証も容易に行えます*⁶。
オンプレミス型システムは高いセキュリティを確保できますが、初期投資と運用コストが高くなります。大規模な展開や長期運用を前提とする場合に適しています。
配信システムには、スケジュール配信機能、緊急時の即座更新機能、効果測定機能などが必要で、制作したコンテンツを最大限活用するための運用設計も重要な要素となります。
●デジタルサイネージ配信システムとは?導入の決めてと注意点!!はこちら
制作時の注意点
駅の特殊な環境を考慮した制作上の注意点があります。音声出力の制限により、視覚的な情報だけで完結するコンテンツ設計が必要で、テキストとビジュアルの最適な組み合わせが重要になります。
また、駅構内の照明条件や視認距離を考慮したデザインが必要で、明度・彩度の適切な調整、文字サイズの最適化、背景とのコントラスト確保を心がける必要があります*³。
駅利用者の移動パターンを考慮し、短時間での情報伝達を前提とした構成が求められます。通勤ラッシュ時の混雑や、乗り換えによる急いだ移動など、駅特有の利用状況に対応したコンテンツ設計が成功の鍵となります。
まとめ
駅デジタルサイネージのコンテンツ制作は、適切な制作プロセスと専門的な技術により、従来の広告メディアを大きく上回る効果を実現できる分野です。しかし、その効果を最大化するためには、駅という特殊な環境に特化した制作ノウハウと、継続的な改善を支える運用体制が不可欠です。
特に重要なのは、3秒ルールに代表される時間的制約の中で、いかに印象的で記憶に残るコンテンツを制作できるかという技術です。これは一般的な映像制作とは大きく異なる専門的なスキルであり、駅サイネージの制作経験を通じて培われるものです。
また、デジタルサイネージの真の価値は、リアルタイム更新や時間帯別配信など、従来メディアにはない柔軟性を活用したコンテンツ運用にあります。これらの特性を最大限活用するためには、制作段階から運用を見据えた設計が必要です。
コンテンツ制作において、社内のリソースや専門知識に課題を感じる場合は、豊富な制作実績を持つ専門会社のコンテンツ制作サービスを活用することが効果的です。プロフェッショナルな制作技術と運用ノウハウを組み合わせることで、より確実で効果的なコンテンツ制作が可能になり、投資対効果の高いサイネージ運用を実現できます。
駅デジタルサイネージのコンテンツ制作は、技術的な複雑さと創造性の両方が求められる分野ですが、適切なアプローチと専門的なサポートにより、必ず期待を上回る成果を実現できる魅力的なメディアです。
専門家によるサポートを活用しませんか?
私たちはデジタルサイネージの導入から運用体制構築まで、トータルでサポートしています。
「効果的な運用を始めたい」「現在の運用に課題を感じている」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
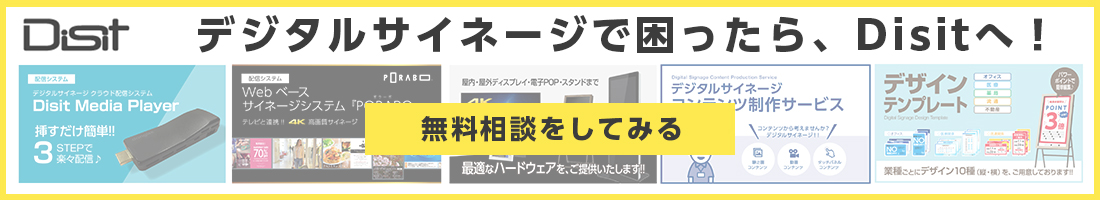
参考文献
*¹広告・出版事業:JR東日本. https://www.jreast.co.jp/life_service/ad/
*²東京メトロ【デジタルサイネージ】 – 交通広告ナビ. https://www.koutsu-navi.com/station/digital/tokyometro/
*³デジタルサイネージのディスプレイサイズ、おすすめの選び方3選 | ニシム電子工業株式会社. https://www.nishimu.co.jp/news_top/blog/signage/04
*⁴駅構内のデジタルサイネージ、接触時間は1.5秒 – アドタイ. https://www.advertimes.com/20101216/article3511/
*⁵駅デジタルサイネージ|費用・効果・メリットを詳しく解説|アドターミナル. https://ad-terminal.tokyo/products/station-digital-signage/
*⁶デジタルサイネージの効果測定と運用改善について | リコー. https://www.ricoh.co.jp/signage/column/retail/03.html
Disitのコンテンツ制作事例
CONTACT
デジタルサイネージのことでお役に立てる自信があります。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:月~金 10:00~17:00/土・日・祝日 休み
『ディジットサイトを見た』と最初にお伝えください。
スムーズに担当者へおつなぎいたします。
STAFF BLOG
スタッフブログ
DISIT(ディジット)のスタッフが書くブログ。
NEWS
お知らせ
製品・サービスのプレスリリース、実績追加、イベント出展などのお知らせ。
|
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
|
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
|
お知らせ
|
新規コンテンツ制作事例を追加しました |
|
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
|
サイネージ
|
飲食店でのデジタルサイネージ導入メリット・デメリットと活用事例 |